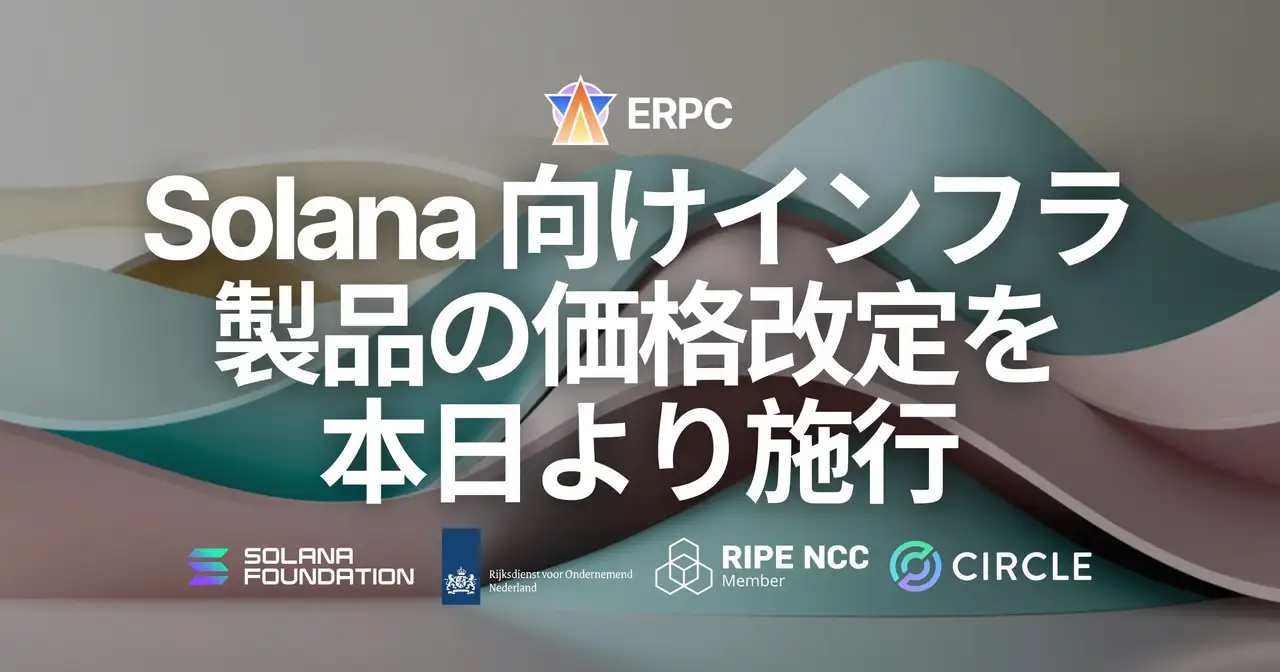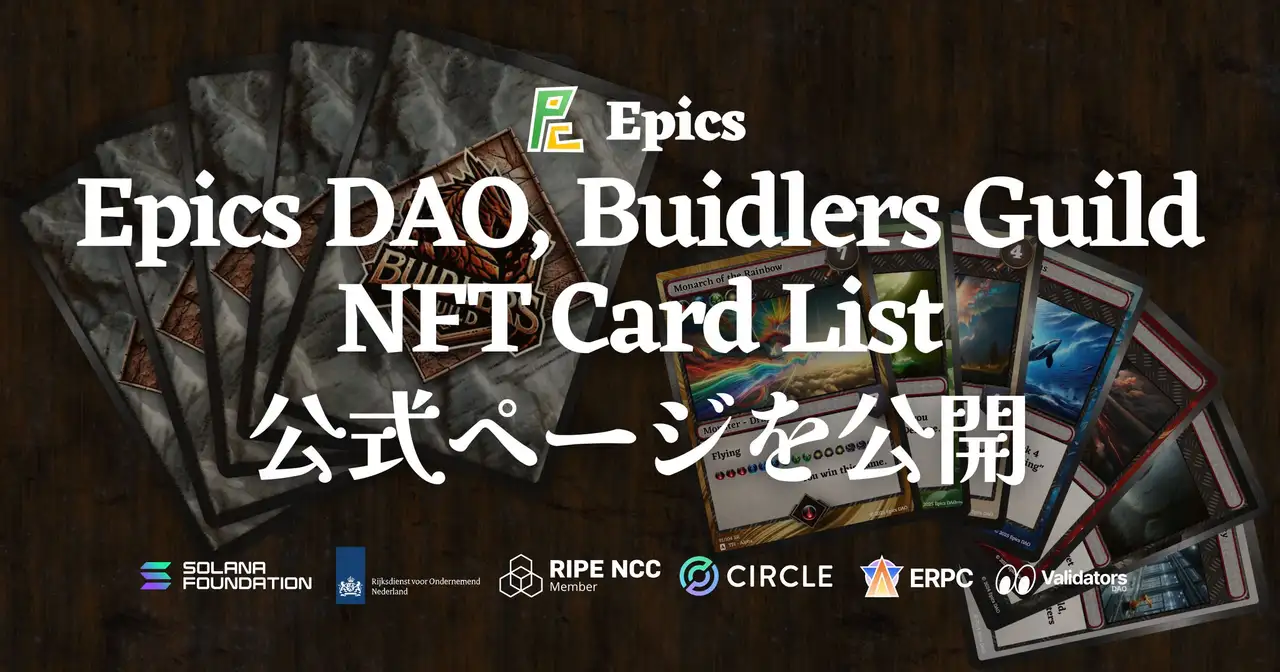Solana 専有ノードと共有ノードの構造的な違いと、最高速を求める際に専有が不可欠となる理由
Solana 専有ノードと共有ノードの構造的な違いと、最高速を求める際に専有が不可欠となる理由
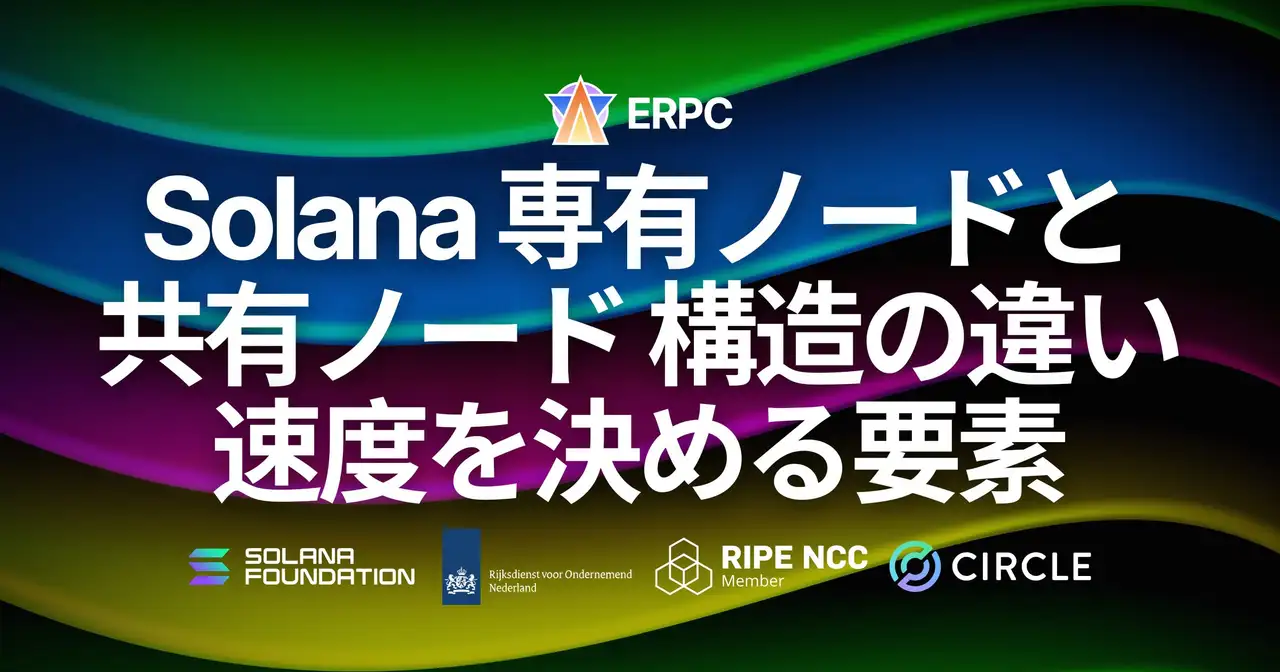
Solana で最高速を狙うとき、コードやアルゴリズムだけでは越えられない壁があります。通信速度を決めているのは、アプリケーションの工夫よりも「距離」「経路」「リソースの割り方」「TLS の有無」といった、より下層の仕組みです。ここを正しく理解しない限り、どれだけ最適化を続けても、共有ノードでは到達できない速度領域が存在します。
本記事では、共有ノードと専有ノードの構造的な違いを整理し、なぜ専有ノードが「本当の最速」を狙うときに不可欠になるのかを説明します。
通信の速さを決めるのは距離と経路
インターネット上の通信は、まず物理的な距離と経路で速さが決まります。途中で経由するルーターやスイッチが増えれば、そのたびにごく小さな遅延が積み上がり、経路が遠回りになれば往復時間は大きくなります。光ファイバー上を進む信号速度には上限があり、この層はどれだけアプリケーション側を工夫しても動きません。
つまり通信の速さは、最初に「どれだけ近いか」と「どの経路を通るか」でおおよそ決まります。そのうえで、同じ距離・同じ経路を前提にしたときに効いてくるのが、ノード内部の構造です。
共有ノードが揺れを生む理由
共有ノードは、強力なサーバーを複数人で同時に使う構造です。32 コアのサーバーを 100 人で共有している場合、同時に処理できる仕事は 32 個までであり、残りは必ず順番待ちになります。OS が高速にタスクを切り替えるため、普段の利用では遅さを意識しないかもしれませんが、内部では常に待ち時間が発生しています。
この待ち時間は、Shreds 等のストリーム受信タイミングやトランザクション送信のタイミングの揺れとして現れます。一般的な dApp やウォレット利用では問題になりませんが、高頻度取引(HFT)などの高速領域では、この数ミリ秒の揺れがそのまま結果に跳ね返ります。
共有ノードが遅いのではありません。「共有する」という構造そのものが、遅延と揺れを必ず生むという点が本質です。
専有ノードが揺れを抑えられる理由
専有ノードは、サーバーを一人で使う構造です。CPU、メモリ、I/O、ネットワーク枠のすべてを自分のワークロードだけが利用するため、他人の処理による順番待ちがほぼ発生しません。
Solana のように Shreds の受信やトランザクション送信のタイミングが一瞬の差で競争を分ける環境では、平均レイテンシの差だけでなく、「どれだけ揺れを抑えられるか」が重要になります。専有ノードは、この揺れを構造的に抑えられるため、同じハードウェアでも共有ノードとはまったく違う速度領域に入ります。
TLS が生む 20ms の遅延
共有ノードでは TLS/SSL が必須です。複数人が同じエンドポイントを使う以上、暗号化を外すと盗聴や改ざん、リプレイ攻撃のリスクが直ちに現実化してしまいます。共有ノードで http を許可することは、サービス設計上もセキュリティ上も不可能です。
専有ノードは利用者が一人に限定されているため、TLS を外して http 通信に切り替えることができます。TLS には暗号化・復号、ハンドシェイクといった処理が必ず挟まり、実測では 20ms 前後の遅延が加わります。この 20ms は共有ノードでは絶対に削れない領域です。
専有ノードでは、揺れの少なさに加えてこの 20ms を丸ごと削ることができるため、共有ノードがどれだけ最適化されていても届かない速度領域に入ります。
共有ノードが担うポジション
共有ノードは、最速を狙うための仕組みではありません。広いリージョンをカバーし、必要十分な速度を低コストで提供するための仕組みです。多くのアプリケーションにとっては、共有ノードが最も現実的な選択になります。
フランクフルトのような主要リージョンだけ専有ノードを置き、東京やシンガポールは共有ノードで補完する構成もよく見られます。常に最高速が必要なわけではなく、「高速であれば十分」な場所と、「絶対に遅れたくない」場所を分けて設計するのは合理的です。
Solana はゼロ距離の場所が常に動く
Solana の特徴として、リーダーバリデータが世界中を移動していくという点があります。その時々のリーダーがどのデータセンターに近いかによって、「今この瞬間のゼロ距離」が変わります。
東京のリーダーがブロックを生成する時間帯は東京近傍が有利になり、フランクフルトがリーダーの時間帯はフランクフルト近傍が有利になります。これはインターネット全体の距離と経路の上に、Solana 特有の「リーダー位置の変化」がさらに乗っている状態です。
この性質のため、別大陸から常に全てのリーダーを追いかける構成では、どうしても物理的に間に合わないスロットが出てきます。Solana で本気で最速を狙う場合、「どの距離を優先するか」と「どこに専有ノードを置くか」をセットで考える必要があります。
ERPC が速度差を最小化できる理由
ERPC は Solana 用途に適したデータセンター選定とネットワーク構成を行い、Jito Block Engine や Shredstream を活用しながら、帯域の確保、NIC 設定、OS チューニングなどを組み合わせて高速化を行っています。
同じソフトウェアを自前で立てた場合と比べても、ゼロ距離構成や経路の最適化により速度差が出ることは珍しくありません。共有ノードでも可能な限り揺れを抑え、専有ノードではその上で http 通信による短縮を積み重ねる設計になっています。
専有ノードを選ぶべき場面
専有ノードが必要になるのは、高頻度取引やアービトラージ、MEV、0 スロットを狙う戦略など、一瞬の揺れが PnL に直結する場面です。距離と経路を詰め、コードも最適化し、それでもなおレイテンシが壁になっている場合、共有ノードの構造的な限界を超えるには専有ノード以外に選択肢がありません。
一方で、一般的な dApp、ウォレット、NFT、リアルタイム性がそこまで重要でない用途では共有ノードで十分です。多くのプロジェクトでは、まず共有ノードから始め、必要になったタイミングで専有ノードを追加する形が現実的です。
共有ノードは妥協ではなく、役割が違うだけです。ただし「本当に最速を取りにいく」という設計に切り替えた瞬間に、構造的に専有ノードが必要になります。
まとめ
通信の速さは、まず距離と経路で決まります。そのうえで、共有ノードか専有ノードか、TLS を使うかどうか、といった構造の違いが差を広げます。共有ノードはコストパフォーマンスとカバレッジを重視した選択肢であり、専有ノードは揺れと TLS の 20ms をまとめて削り、「本当の最速」を狙うための選択肢です。
Solana では、リーダーバリデータの位置によってゼロ距離の場所が常に移動します。この特性と、距離・経路・ノード構造の違いを踏まえたうえで、自分の戦略に必要な速さを満たす構成を選ぶことが重要です。
ネットワーク距離の最適化や構成相談については、Validators DAO 公式 Discord で受け付けています。
- ERPC 公式サイト: https://erpc.global/ja
- Validators DAO 公式 Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR